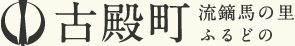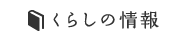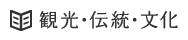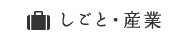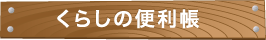飛鳥時代・奈良時代・平安時代
| 町・県のできごと | 時代 | 西暦 | 国内のこと |
| 飛鳥時代 | 538 | 百済から仏教伝わる | |
| 593 | 聖徳太子摂政となる | ||
| 陶棺つくられる (いわき市) |
|||
| 金冠塚古墳築かれる (いわき市) |
607 | 法隆寺建てられる | |
| 蝦夷穴古墳築かれる (須賀川市) |
630 | 初めて遣唐使中国へ行く | |
| 中田横穴の壁画かかれる (いわき市) |
|||
| *白鳳時代 | 645 (大化1) |
大化改新 | |
| 泉崎横穴の壁画かかれる (泉崎村) |
|||
| 672 | 壬申の乱おこる | ||
| 701 | 大宝律令つくられる | ||
| 708 | 和同開珎鋳造 | ||
| 福聚寺銅造り観音菩薩立像つくられる (喜多方市) |
|||
| *天平時代 | 奈良時代 | 710 (和銅3) |
奈良に平城京をきずき都を定める |
| 石城・石背国がおかれた | 718 (養老2) |
養老令がつくられる | |
| 借宿廃寺建立と考えられる (白河市) |
728 (神亀5) |
||
| この頃、上人檀廃寺建立される (須賀川市) |
この頃、多賀城がつくられる | ||
| この頃、慧日寺白銅三鈷杵つくられる (磐梯町) |
714 -768 (神護景雲1) |
国々に国分寺・国分尼寺がつくられる | |
| この頃、能満寺、木心乾漆虚蔵座像が奈良でつくられる (いわき市) |
|||
| 安積山、安達太良山、会津嶺、真野萱原など萬葉の歌によまれる | 770 | 頃、萬葉集編さんされる | |
| この頃、白河神社をはじめ諸社が崇敬される | 780 (宝亀11) |
||
| *平安前期 | 平安時代 | ||
| この頃、泉廃寺建立される (原町市) |
794 | 平安京がきずかれ、都が京都に移される | |
| この頃、腰浜廃寺建立される (福島市) |
|||
| この頃、横手廃寺建立される (鹿島町) |
802 | 坂上田村麻呂、胆沢城を築く | |
| 805 | 最澄、天台宗を開く | ||
| 806 | 空海、真言宗を開く | ||
| 僧、徳一、会津慧日寺に住した | 817 (弘仁8) |
||
| 山階寺の知興が開いた信夫郡菩提寺が定額寺となる | 830 (天長7) |
||
| 八溝山の産金遣唐使の資となり、八溝黄金神社封戸を奉られる | 836 (承和3) |
||
| この頃、勝常寺木造薬師如来坐像つくられる (湯川村) |
866 | 応天門の変おこる | |
| この頃、円仁が霊山寺を開いたといわれる (霊山町) |
|||
| 安積郡弘隆寺天台別院となる | 881 (元慶5) |
||
| 延喜式神名帳に県下36社が登録される | 905 -907 (延喜7) |
古今和歌集編さんされ、延喜式撰集される | |
| この頃、勝常寺四天王・聖観音立像などつくられる (湯川村) |
|||
| この頃、大蔵寺木造千手観音立像つくられる (福島市) |
937 | 平将門の乱おこる | |
| この頃、法用寺木造金剛力士像つくられる (会津高田町) |
|||
| この頃、法用寺木造十一面観音立像つくられる (会津高田町) |
1017 | 藤原道長、太政大臣となる。 藤原頼通、摂政・関白をつとめる |
|
| この頃、宇内の木造十一面観音立像つくられる (会津坂下町) |
1051 | 前九年の役おこる (源頼義が奥羽守る・鎮守府将軍として任地に下り、子の義家とともに陸奥の豪族、安倍氏を滅ぼした。) |
|
| この頃、竜興寺一字蓮台法華経つくられる (会津高田町) |
|||
| この頃、泉福寺木造大日如来坐像つくられる (山都町) |
|||
| この頃、表郷一小保管瑞花双鳥八稜鏡つくられる (表郷村) |
|||
| 1053 | 宇治平等院つくられる |